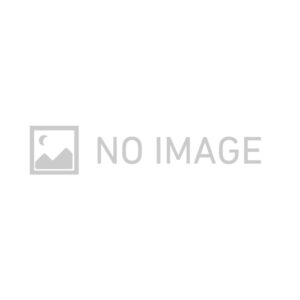従属請求項を作成するメリット(その1)
先般のセミナーで「従属請求項を作成するメリットは何か?」という質問を受けました。
この機会に、従属請求項を作成するメリットについて書きたいと思います。
メリットとして代表的なものを3つ挙げました。
(1)どの構成に特許性があるのか探るため
(2)無効のリスクを避けるため
(3)上位の請求項(独立請求項)が狭く解釈されるのを防ぐため
今回は(1)と(2)について説明し、(3)は別の記事で紹介したいと思います。
(1)どの構成に特許性があるのか探る
まず、以下のように、請求項1しか記載せずに出願した場合を考えます。
【請求項1】
脚部と、座部と、背もたれと、を備える椅子。
審査を受け、請求項1に「新規性なし」の拒絶理由が通知されたとします。
拒絶理由を解消するためには、請求項1に何かしら限定を加える必要がありますが、どのレベルまで限定すべきか判断が難しくなります。
できる限り広い範囲で権利を取りたいため、あまり限定したくはないですが、一方で、限定しなさすぎると拒絶となってしまいます。
次に、請求項1に加え、請求項2および3も記載して出願した場合を考えます。
このケースでは、請求項2と請求項3が従属請求項になります。
【請求項1】
脚部と、座部と、背もたれと、を備える椅子。
【請求項2】
肘掛けをさらに備える、請求項1に記載の椅子。
【請求項3】
キャスタをさらに備える、請求項1に記載の椅子。
上記のように、請求項1に加えて請求項2および請求項3も記載しておけば、請求項1(拒絶理由あり)、請求項2(拒絶理由あり)、請求項3(拒絶理由なし)のように、請求項ごとに特許性の有無について知ることができます。
このように、従属請求項を作成しておくことで、各請求項に係る発明についての審査官の判断を知ることができます。
(2)無効のリスクを避ける
特許権の成立後、他社は、無効審判によって特許権を潰しにくることがあります。
仮に、請求項1しかなかった場合、請求項1が無効と判断されれば、特許権全体が無効になります。
訂正の請求で請求項1を限定することもできますが、(1)で述べたように、どのレベルまで限定すれば無効が回避できるのか判断に困るところです。
なお、請求項の数を増やすこと(従属請求項を新たに作ること)は認められていません。
そこで、(1)で示したように、あらかじめ請求項1に加えて請求項2および請求項3も記載しておけば、請求項1(無効理由あり)、請求項2(無効理由あり)、請求項3(無効理由なし)と判断された場合、請求項1および2を削除し、請求項3だけを残すことで、無効を回避できます。