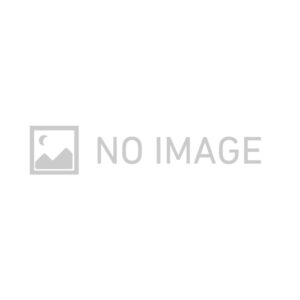従属請求項を作成するメリット(その2)
前回の記事に引き続き、従属請求項を作成するメリットについて説明します。
今回は、「(3)上位の請求項(独立請求項)が狭く解釈されるのを防ぐため」についてです。
具体的な事案で説明した方が分かりやすいと思いますので、裁判例を見ながら説明します。
・大阪地判令和3年(ワ)第1720号 特許権侵害差止等請求事件
特許第5713127号の請求項1および2は以下の通りです。
【請求項1】
・・・発電要素・・・を有する電池。
【請求項2】
前記発電要素は、巻回型の発電要素である
請求項1記載の電池。
「電池」に関する発明です。
請求項1では、「発電要素」の形状に関し、限定は加えられていません。
一方、請求項2では、「発電要素」の形状が「巻回型」に限定されています。
被告は、明細書や意見書の記載から、請求項1の「発電要素」は「巻回型」に限定されるべきと主張しました。
ちなみに、被告製品の発電要素は「積層型」であったため、仮に請求項1の発電要素が「巻回型」に限定解釈されれば、文言侵害はないという事案です。
これに対し、裁判所は、以下の通り判断しました。
『本件特許1の特許請求の範囲請求項1は、発電要素の形状について特定していない一方、請求項2は、「前記発電要素は、巻回型の発電要素である請求項1記載の電池。」と特定していることから、本件発明1の発電要素は、特定の形状に限定されるものではないと理解するのが自然である。』
別の裁判例も見てみましょう。
・東京地判平成22年(ワ)第17810号 特許権侵害差止等請求事件
『ここで,本件特許権の請求項2の発明は,「・・・当該キャリッジが前記レール手段(7)の中 央に向かって共に移動されることを特徴とする請求項1の装置」(甲2の 3・17頁,乙9・22頁)というものであり,請求項1の発明(本件発 明)を中央展開方式に限定した請求項になっているのであるから,本件発明 が,請求項2の中央展開方式に限定されない発明であることは明らかである。』
このように、独立請求項を限定した従属請求項を作成しておくことで、独立請求項が限定解釈されるのを避けることができると考えられます。
前回および今回の記事で、従属請求項を活用することで、様々なメリットがあることがご理解頂けたかと思います。