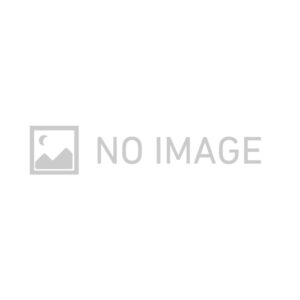よくある勘違い
引き続き、セミナーでの話題です。
セミナーで以下のクイズを出しました。
<事例>
X社は、『脚部と、座部と、背もたれと、を備える椅子。』の特許権を保有している。
Y社は、『脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子。』の特許権(X社よりも後に出願)を保有している。
クイズ:『上記事例において、Y社は、自社の特許権に係る製品(脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子)を製造販売できるか?』


多くの受講者の方は、『できる』と回答されました。
『「できる」と回答した理由は?』と聞くと、『Y社は、(肘掛け付きの椅子の)特許権を持っているから』とのことでした。
はい、これ間違いです。Y社の製造販売行為は、X社の特許権を侵害します。
なぜなら、Y社が肘掛け付きの椅子を製造すれば、X社の特許権である『脚部と、座部と、背もたれと、を備える椅子』を実施することになるからです(このような関係を「利用関係(または利用発明)」と言います)。
実は、特許に馴染みのない方にとって、この間違いは非常に多いのです。
当職はこれまで、以下のような認識の方に何度か出会いました。
・特許を持っているのだから、その権利範囲内で製造販売等していれば、他社の権利を侵害することはない
・特許が取れたということは、他社の権利を侵害していないことの証だ(他社の権利を侵害していないから、特許が取れたんだ)
その考え方は違いますよと説明すると、皆さん『えっ?』と驚かれます。
Y社が自社製品(脚部と、座部と、背もたれと、肘掛けと、を備える椅子)を製造販売するためには、X社から特許権のライセンスを受けるか、X社の特許権を潰すしかありません。
このように、特許権を持っていたとしても、その特許権に係る製品を製造販売できない場合があることにご留意ください。